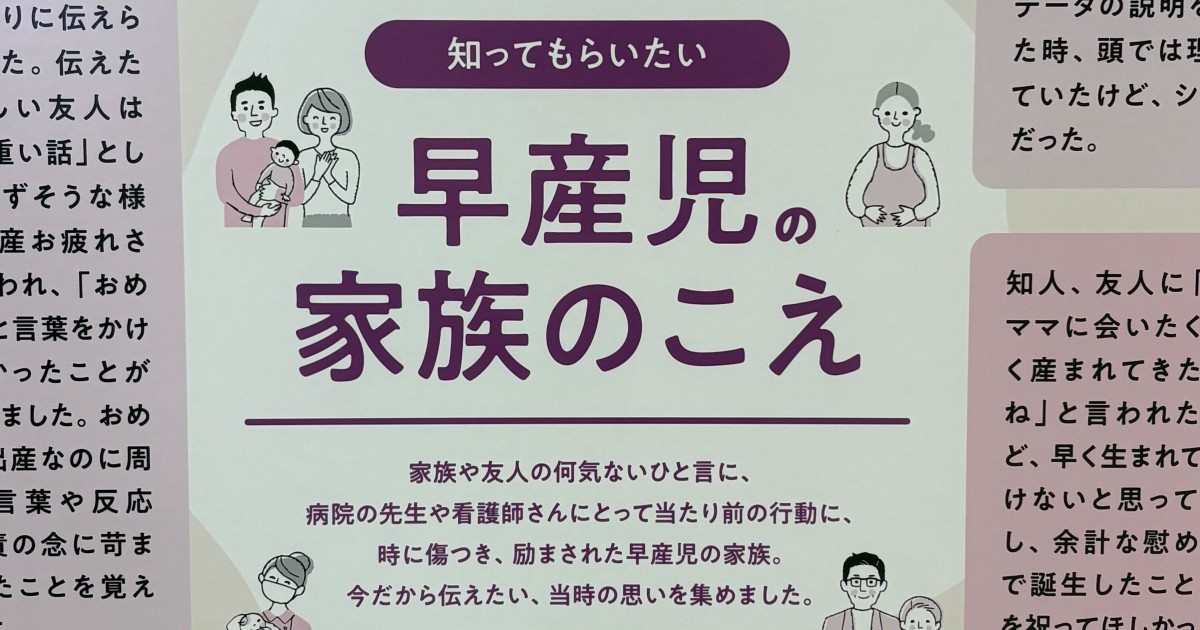「こんなのアリ?1番不快なお祈りメール」カタカナの名前の学生が涙 就活で受けた悪意なき差別
《ハーフだけど日本生まれ日本育ち国籍日本なのに向こうから急に説明会キャンセルされたんだけど!!!こんなのアリなん😭😭😭😭😭1番不快なお祈りメールだが😭😭😭😭》
今から3年前の就活シーズン中、牛丼チェーン「吉野家」の就職説明会をめぐる女子学生の投稿がSNS上で話題になりました。

吉野家から届いたメールについて問題提起した女子学生のSNS投稿=2022年、本人提供
投稿文に「ハーフ」とある通り、彼女は外国籍の父と日本国籍の母がいて、日本で生まれ育ちました。
ところが、吉野家から就活生に届いたメールの内容を見ると、外国籍の就労ビザ取得が難しいことを理由に、就職説明会への予約をキャンセルする旨が書いてあります。吉野家が根拠なく、就活生のことを外国籍だと決めつけていたのです。
当然のことですが、そもそも仮に外国籍だったとしても、外国籍を理由に参加を断ること自体が、人種差別を禁じた憲法違反になりえます。
厚生労働省の職業安定局就労支援室の担当者に取材すると、外国籍を理由に就職関連の制限をすることは「望ましくない」という認識を示しています。
この問題の背景には、ミックスルーツと外国人への二重の差別意識があると言えるのです。

吉野家から女子学生に届いた説明会キャンセルのメール=2022年、本人提供
よそ者扱いは日常茶飯事
母が中国ルーツというミックスルーツの当事者でもある筆者自身は、就活で差別を受けたことはありませんでしたが、海外ルーツを理由に「よそ者」扱いされることはよくありました。
たとえば、何の脈絡もなく「中国で暮らした方が相性良いんじゃない?」「半分は中国製だね」などと言われたことを覚えています。
ただ、そうした差別が表面化することは少なく、吉野家の問題はレアケースだったと言えます。
ミックスルーツの当事者はどう思っているのか――。それを知ってもらえる機会になればと思い、取材を申し込みました。
彼女は当時、次のように話してくれました。
「就活サイトを通じてエントリーしたのですが、国籍や顔写真を登録する項目はありませんでした。私は姓も名もカタカナなので、それだけで外国籍だと決めつけられたのだと思います。ショックな気持ちが大きかったです」
「今回のような差別は、吉野家だけの問題ではありません。日本人の中にも色々な人がいるということを、頭の中に置いといて頂けるとうれしいです。私自身、小さい頃から、色々な視線を浴びてきたんですけれども、みんながもっと生きやすい世の中になればいいなと考えています」
彼女の言うように、こうした問題は今回に限ったものではありません。
関西学院大学人権教育研究室が海外ルーツの就活経験者105人を対象にした2021年のアンケートによると、4割が国籍や名前などに関する差別・偏見を感じたと答えています。現在も就活をめぐる差別は少なくないのです。
歴史的にも、在日コリアンの人々への就職差別はひどく、1970年代には在日2世だと告げた男性が採用を取り消され、訴えたケースもありました。
会社側は、採用試験で在日としての民族名ではなく日本名を使っていたことなどが社内ルールに反すると説明しましたが、裁判所は判決で「在日朝鮮人が置かれている歴史的社会的背景を考えると、出生以来使っていた日本名を使用したからといって企業が解雇する理由にはならない」との主張を全面的に認め、後に男性側の勝訴が確定しました。
「私のように嫌な思いをする人、減ってほしい」
残念ながら、昨年も、吉野家の時と同じような問題が起きました。
あるコンサル企業に応募したミックスルーツの専門学校生のもとに、《大変申し上げにくいのですが、弊社では留学生さんの採用はおこなっておりません》として、選考への参加をキャンセルしたと伝えるメールが届いたのです。
今回も、カタカナの名前から外国籍だと判断されたようでした。
学生はナイジェリア人の父と日本人の母がいて、国籍は日本です。姓は父のもので、ひらがなのファーストネームは母が「愛らしく」、カタカナのミドルネームは父が「幸せに生きてほしい」という思いを込めて名づけてくれたそうです。
筆者が取材すると、学生は「多様なルーツを持つ日本人の存在を知ってもらい、私のように嫌な思いをする人が減ってほしい」と話してくれました。

ナイジェリア人の父を持つミックスルーツの学生=2024年5月、東京都内
記事には、SNS上などで大きな反響がありました。
NPO法人青少年自立援助センターの田中宝紀さんは、記事のコメント欄で「このような出来事は、この専門学校生の方をはじめ、多くの海外ルーツの方が直面する『日常』の一場面となっています」と指摘した上で、「『悪意のない(とマジョリティは言う)無意識の差別』(マイクロアグレッション)に日々晒されることが積み重なり、いつしか大きな傷となってしまうことを、どうしたらマジョリティが理解し行動に反映できるようになるのか」と投げかけています。
田中さんが指摘するとおり、取材してきた筆者の実感から言っても、差別は、日常生活のなかでの何げない一言から引き起こされることが多いです。
その日々の差別が、就活という表舞台で露見したに過ぎないのです。
3月1日配信のレターでは、筆者が飲み会の席で、差別に加担してしまった苦い経験を振り返り、差別が起きる背景について考えます。
小川尭洋(おがわ・たかひろ)
朝日新聞のデジタル企画報道部記者。中国人の母と日本人の父を持つ「日中ハーフ」の視点から、多様なルーツを持つ人々を取材しています。
X:@ogawat0802
Instagram:@ogawakisha
すでに登録済みの方は こちら